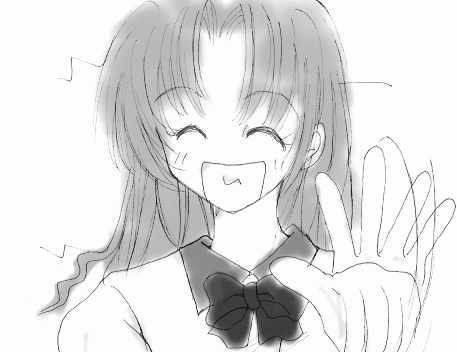
|
「や、やだな。なに言ってんのよキョーコったら」 途端、かなめは喉の奥で空気が詰まったような声を出した。 こちらからの言葉を制止するように、左の手のひらを向けると、 「んなワケないでしょ!? なに勝手に勘違いとかしてんのよ」 「えーでも、ほらこの間だって――」 「あー、あれは、ほら! ソースケがまずそうな食事ばっかりしてるから」 「うー、たしかにおいしそうではないよねえ、あれは」 つい先日などは、細い茶筒のような中から、小さな固形ビスケットのようなものを取り出すと租借し、さらに意図の不明な棒が登場したかと思えば、次に取り出した缶ジュースのようなものにつきたてていた。 それはさながら、なにかの宗教の妖しげな儀式ようであった。 「だからね、別に関係なんかないってのよ。う、うはははは!」 |
→